目下、急成長中の音楽配信市場。2012年に設立された国内デジタルディストリビューターの先駆けTuneCore Japan(以下、TCJ)が5月に公開した統計「MUSIC YEARLY STATS 2020」によると、2020年のアーティスト、レーベルへの還元額は前年比168%の71億円に達し、累計では170億円に到達したという。
これは近年のストリーミングサービスの普及を前提に、YouTubeやTikTokといったエコシステムが整備されたこと、コロナ禍がデジタルの利用を後押ししたことなどが原因だと考えられるが、何よりインディペンデントアーティストの継続的な活動を支え続けてきたTCJ自身の功績だといえよう。
そんなTCJのスタートから9年が経過し、現在では国内にも複数のデジタルディストリビューターが存在するが、そのなかで最も新しい部類に入るのが、音楽プロダクションのHIP LAND MUSICが2019年に立ち上げたFRIENDSHIP.。キュレーターがアーティストをセレクトし、それぞれに最適化したサポートを展開するレーベル的な性格が強く、TCJとは異なるアプローチだが、アーティストやリスナーにその違いはまだ十分に伝わっていないかもしれない。
そこで今回はTCJ代表の野田威一郎と、FRIENDSHIP.の山崎和人を招き、あらためて現在の音楽シーンにおけるデジタルディストリビューターの役割を紹介するとともに、それぞれの目指す方向性について語ってもらった。
瑛人“香水”のヒットは、コロナ禍がきっかけ?
―TCJが公開した「MUSIC YEARLY STATS 2020」によれば、昨年のTCJからアーティストへの還元額は前年比166%の約71億円とのことで、これはデジタル配信全体の伸びを表しているといってもよいかと思います。あらためて、2020年を振り返っていただけますか?
野田:あの統計は毎年出しており、じつは伸び率でいうと2020年より2019年の方が伸びてるんです(2019年の伸び率は170%)。ただ、2019年は42億円だったのが、2020年は71億円で、金額の規模が大きくなっているにもかかわらず、ほぼ伸び率が変わってない状況なんですよね。
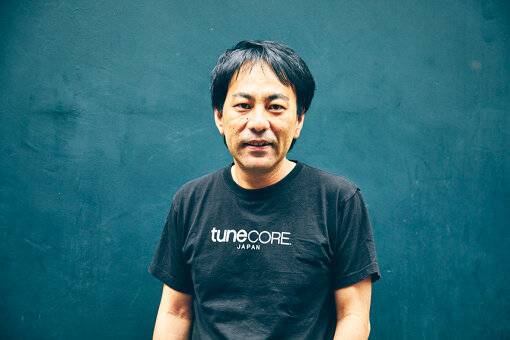
東京出身。香港で中学・高校時代を過ごし、慶應義塾大学卒業後、株式会社アドウェイズ入社。2008年に独立しWano株式会社を設立。2012年にはTuneCore Japanを立ち上げ、2012年10月にサービスを開始。
野田:なおかつ、この伸び率はレコ協(日本レコード協会)さんが出されている2020年の配信の伸び率よりも高いので、ぼくらが扱っているようなインディペンデントアーティストが活躍した年度だったのは事実だと思います。
―具体的には、どんなアーティストの活躍が顕著でしたか?
野田:やっぱりTikTokで流行ったアーティストの存在は大きくて、緊急事態宣言中に瑛人、その後にりりあ。さん、yama、BLOOM VASEとか、TCJを利用してくれているインディペンデントなアーティストがマスメディアにも露出するようになったのは、2020年の大きな変化だったと思います。特に“香水”のヒットに関しては、コロナの影響が大きかったんじゃないかなと、個人的には思っていて。
BLOOM VASE『BLOOM iSLAND』を聴く(Spotifyを開く)
―というと?
野田:昨年4月、5月は業界関係なく、全員家にこもったじゃないですか? それを機に普段はテレビや劇場などで忙しかった芸人や著名人もTikTokやYoutubeなどの新しいチャネルに参加するようになり、若年層に受けていた“香水”がさらに、ネタとして利用された結果、さらなる層に広がっていった。そういう楽曲自体がオンラインメディアで横展開されるきっかけになったのが、去年の自粛期間だったかなと思います。
―FRIENDSHIP.から見た2020年はどんな一年でしたか?
山崎:FRIENDSHIP.は2019年にスタートしていて、ちょうど一年経たないくらいでコロナが世界で流行してしまったので、思い描いていた外向けのアウトプットの大半ができなくなってしまったというのがありました。
そもそもそれまでの日本はCDとデジタルを同時リリースして、プロモーションしていく文化がまだ残ってたと思うんですね。だから、お店に人が呼べない、ライブもできないというなかで、「じゃあ、配信リリースも一回止めましょう」ということが、2020年の前半に起こって。
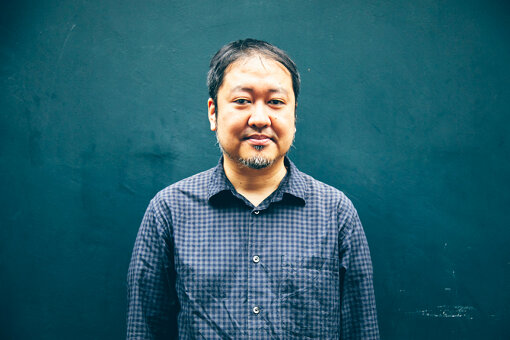
1978年生まれ。2000年、株式会社ハーフトーンミュージック入社、2003年よりライブハウス「新宿MARZ」店長 / ブッキングマネージャーを経て、2009年に株式会社ヒップランドミュージック・コーポレーション入社。The fin.、LITEのA&R / マネージャーとして、作品リリースやアメリカ、ヨーロッパ、アジアなど数々の海外ツアーの制作を担当。2019年5月より、デジタル・ディストリビューションとPRが一体となったレーベルサービス「FRIENDSHIP.」をスタートさせる。
―確かに、一時期はいろんな動きがストップしてしまって、それはまだCDとデジタルがセットだったからだと。
山崎:でも、「しばらく何もできないな」という状況をみんなが認識してからは、一気に表現の場がストリーミングやライブ配信に切り替わって、それからFRIENDSHIP.への応募も急激に増えましたね。
あとは、アーティスト自身が活動のプランを考えるようになった一年だったんじゃないかなって。以前までは、音をつくるのは自分たちがやるけど、それ以降はレーベルや事務所にお任せするという認識のアーティストが多かったと思います。でも、コロナ禍を経て、全部を自分たちでコントロールしようという意識の芽生えたアーティストがすごく多かった気がしますね。
収益は100%還元。アーティストの継続的な活動を支えるTuneCore Japan
―あらためて、それぞれのサービスの成り立ちをおうかがいしたいのですが、TCJの設立は2012年で、まさに日本のデジタルディストリビューターの先駆けですよね。
野田:そもそもCDを流通させるには、事務所やレーベルに所属して、流通会社を使う必要があったわけです。それでやっとタワーレコードやHMVにCDが並ぶっていう、音楽業界の決まった流れがあったわけですけど、どこかに所属しなきゃいけないとか、地方だとそもそも大変とか、いろんな弊害があったんですよね。
そんななか、世の中にオンラインが普及してきて、自分でつくった曲を個人でアップロードできるようにはなったものの、無料配布はできても、有料で、オフィシャルで発表できる方法がまだなかった。それをデジタルのサービスを使って解決したのが我々だと思っています。
会社を立ち上げた頃はまだストリーミングがなかったので、「何をどこに流通してるんだ?」と思われたかもしれないですけど(笑)、当時の主流はダウンロードで、iTunesだったり、AmazonのMP3だったりしました。それから4年後、日本のストリーミング元年といわれている2016年から、さらにサービスが広まっていく流れになりましたね。

―会社として大事にしていたのはどんな部分でしたか?
野田:ぼくたちのミッションは、インディペンデントのアーティストが自分たちで楽曲を発表して、継続的な活動をできるようにすることなので、収益を100%還元するということがコンセプトとしてずっとあります。その代わり、ぼくたちは手数料をちゃんといただいて、それを使ってサービスを拡充するという役割分担です。
あとは、制作資金を出す代わりに権利をもらうのではなく、権利はアーティスト側が持つ。あくまでアーティストが自由に活動できるように、クリエイティブには一切かかわらないっていう、そのコンセプトもずっと変わらないですね。
アーティストを中心とした世界標準の活動を模索するFRIENDSHIP.
―FRIENDSHIP.は2019年のスタートなので、現在の日本のデジタルディストリビューターのなかでも後発組といえますが、そもそもはどんな成り立ちだったのでしょうか?
山崎:ぼくはもともとThe fin.というアーティストのマネージャーをずっとやっているんですけど、彼らが2016年の後半に拠点をロンドンに移して、向こうに住んで活動を始めて。そうなったら、現地のレーベルがついてないとプロモーションもできないと思ったので、向こうの音楽関係者といろいろ話をしたときに、「アーティスト自身でレーベルをつくって楽曲の権利を持ち、デジタルディストリビューターと一緒に仕事をしたら?」と、みんなから言われたんです。
The fin.“Shine”を聴く(Spotifyを開く)
山崎:それから自分でもいろいろ調べるなかで、現地のディストリビューターを紹介してもらい、説明を聞いたら、「ひょっとして、これ自分でできるんじゃないか?」という内容だったんですよね。当時はもうイギリスもアメリカも、アーティストを中心にチームを組んで活動することがスタンダードになっていて、それこそデジタルディストリビューションもそうだし、PR会社やブッキングエージェントとの契約もアーティストが直接行うやり方が普通だったんです。

―でも、日本はまだそうじゃなかった。
山崎:そうですね。レコード会社とマネジメントがはっきり分かれていました。でも、もっとアーティスト主体で活動すれば、日本のどこにいたって海外にまで届けられる。なので、その学びをローカライズしたというか、日本の音楽業界に当てはめてスタートしました。デジタルディストリビューションが根底にありつつ、その周りにプロモーション、出版管理、フィジカルの製造や流通のサポート、マーチャンダイジングなどいくつかのオプションに分けて、必要なアーティストが必要に応じてそれを使う、みたいなかたちです。
―そのあたりがTCJとの条件面での違いにも表れているわけですよね。
山崎:FRIENDSHIP.はアーティストに収益の85%を戻す契約になっていて、その代わり固定費や追加の金額は一切ありません。そうなると、FRIENDSHIP.としては楽曲が再生されないと売り上げにならないわけです。だからこそ、配信するアーティストは応募していただいたデモのなかからこちらでセレクトさせてもらう代わりに、責任を持ってサポートする、というかたちになってるんです。
「配信に対する業界の意識が変わった」(野田)
―TCJのスタートから9年が経過して、現在は日本にも複数のデジタルディストリビューターが存在します。野田さんはそれについてどのように捉えていますか?
野田:海外も同じような状況なので、こうなることはわかっていました。要は、ディストリビューターに求められる役割と環境が変わってきた中で、それぞれの会社がどこにポジショニングするかということだと思っていて。ただ、ぼくらはあくまで「流通」として始めていて、個人でも法人でも使えるので、レーベルや事務所にも使ってもらいたいというスタンスではあったのですが、案外そうはならなかったというのはあります。
―FRIENDSHIP.もそうですけど、レーベルや事務所が独自にサービスを始めていますね。
野田:そもそもレーベル事業の役割のなかに「流通」も組み込まれているわけですよね。ただ、ぼくらはそこに特化した新しい仕組みを始めたので、収益は100%還元はするわけですから、利用してもらえたらいいと思っていたんです。

野田:流通に関する細かい作業はTCJが受け持つので、レーベルや事務所にはその分のお金を制作やプロモーションに——さらにいえば、世界に向けて突っ込んでほしいというのが最初の狙いだったんです。そうすることで業界全体が活性化する、そう思っていました。しかし、現状の実態としてはそれぞれがバラバラに動いてしまっているので、業界としての強度が弱くなっているのではないかと感じています。もちろん、たくさんのレーベルや事務所にも利用していただいておりますが。
―単純に競合が増えて困るというだけでなく、音楽業界全体にとってマイナスになってしまわないかを危惧していると。
野田:ぼくらはもともと流通だけに特化してたんですけど、競合が増えてきたので、提供するサービスを拡大しないといけない状況になってきてるんですよね。
―難しい舵取りですね。
野田:まあ、デジタル音楽の環境もどんどん変わっていくわけで、いろんなニーズが出てきて、それへの対応を随時やってきたなか、自然と変化していったということでもあると思います。9年前と明らかに状況が変わったというのは、それだけ配信に対する業界の意識が変わったということ。だから競合が増えたのは歓迎すべきでもあるはずで、ぼくらがそのきっかけになれたのであれば、いいことだと思うんですけどね。
「これまでのレーベルの代わりになるような、次の何かに手をかけてる感じがして、そこが面白い」(山崎)
―ポジショニングというお話がありましたが、FRIENDSHIP.は自分たちの立ち位置をどのように認識されていますか?
山崎:ぼくたちは「流通」というよりも、どちらかというとレーベルサービスに近い方向性なので、最初のスタートラインがちょっと違っています。もともとのイメージとしては、インディレーベルとディストリビューターの中間の立ち位置でした。
FRIENDSHIP.で特徴的なのが、各アーティストに担当者がいるんです。その担当者がアーティストごとにリリースやプロモーションのプランを考えるので、「アーティストの数だけFRIENDSHIP.内にレーベルがある」みたいな、ちょっとしたコミュニティーみたいな感じになっていて。
―イギリスのAWAL(Artists Without A Label)にも近いイメージですね。
山崎:いまはFRIENDSHIP.というコミュニティーにアーティストが音を持ってきてくれて、それを一緒にリリースして、サポートしていくような感じなんですよね。なので、当初思い描いていたイメージとも違うんですけど、これまでのレーベルの代わりになるような、次の何かに手をかけてる感じがして、そこが面白いと思っています。
野田:選んだアーティストに対してお金を出して、一緒に制作をしてたりもするんですか?
山崎:いや、それはしてないです。原盤にはタッチせず、著作権の管理は希望者に対してサポートしますけど、もちろん何か契約で縛るということはないです。

野田:そこが大きいですよね。以前はレーベルが先行投資して、その分権利をもらっていた。昔は音源をつくるのに個人では払えないような額がかかったので、しょうがなかったけど、いまはMac——何ならiPhoneがあれば音がつくれちゃう。それなのに昔と同じような条件なのはおかしいし、だから我々のような流通会社も必要だったわけです。
―山崎さんは国内のディストリビューターが増えた現状をどう捉えていますか?
山崎:選択肢が増えたというのは、アーティストにとっていいことではあると思います。ただ、プレイリストに入るか入らないかで再生数が大きく変わったりするなかで、「ここから配信してもあんまり再生されなかったから、次はあっちで」みたいに、作品単位で動くアーティストも増えてきました。
ぼくらとしては長いスパンで考えていても、アーティストは目の前の再生数を見て、そこですれ違ってしまう。もちろん、他から出してハッピーになればそれで問題ないですけど、現状より数字が下がってしまうことも多くて。そうなるとアーティストのモチベーションが下がり、その人の才能をちゃんと届けられなくなってしまうので、もったいないなと思います。

野田:それは音楽業界に限らず、いろんなサービスが乱立するようになったデジタルの弊害ですよね。なので、これからはアーティストにもリテラシーが求められる時代になると思います。
「ここはちゃんと手数料相応のケアをしてくれる」とか、自分たちにとって一番いい場所を探していく作業が必要になる。サポートする側も、あっちに行ったりこっちに行ったりするアーティストを、腰を据えてサポートするのは難しいと思うから、そこは人と人の話でもありますよね。
―そういう意味では、やっとスタート地点に立ったということかもしれませんね。選択肢があること自体は正常なことで、そのうえでリテラシーを上げていくフェーズに来た。
野田:そうですね。ここからさらに面白くなっていくと思います。そのためにも、やっぱり原資をつくらないといけないから、全体の規模をもっと大きくする必要がある。まずは国内のストリーミング利用人口を増やすことが音楽業界全体のミッションだと思います。そして、世界へ市場を広げることで、少しでもCD売上の下げ幅をカバーする。
なので、これまで「CD買ってね」と言っていたアーティストに「聴き放題入ってね」と言ってもらったりして、母数を上げていく必要がある。それはDSP(Apple MusicやSpotifyなどのプラットフォーム)側の仕事でもあるけど、そうやってみんなで啓蒙していくことが重要だと思います。
ワールドツアーが組めるかどうかは、シングルよりアルバムのヒットが重要
―国内の話の一方で、いかに日本のアーティストが海外でも普通に聴かれるような状況をつくるかというのは、TCJとFRIENDSHIP.双方にとって大きなミッションかと思います。現状の手応えと、今後の展望をうかがいたいです。
野田:ぼくらにもサブミット機能(資料をDSP側にアップロードする機能。新譜リリースをサブミットすることで、バナー掲載やプレイリスト入りなど、楽曲が展開・紹介されやすくなる)があったり、海外のDSPと交渉したり、できる範囲でのプロモーションはやっていますが、アーティスト本人でプレイリストにピッチ(プレイリストに曲を申請すること)をしたり、地道にやっている子がしっかり成功するようになってきたと思います。
ちょっと前だと、cinnamonsがTikTokを使って海外で聴かれた事例がありましたけど、最近だとHIMIの曲がSpotifyの「Chill Vibes」というプレイリストに入って。フォロワーが200万人くらいいて、アジアから選ばれている曲も少ないプレイリストなので、特筆すべき事例だったなと。
プレイリスト『Chill Vibes』を聴く(Spotifyを開く)
野田:やっぱり、どのジャンルのどういうプレイリストに、どのタイミングで載りたいかって、アーティスト本人が考えるのがベストだと思うんですよね。ぼくらが全員分をピッチするのは無理ですけど、TCJのオンラインメディア「THE MAGAZINE」でアーティスト向けの情報は発信しているので、ぜひ活用してもらいたいです。
こういうプロモーションに関する質問はアーティストからよくもらうんですけど、実際にそれを実行に移す人は本当に少ないので、それを代わりにやるレーベルや事務所のようなチームの存在もアーティストによってはやっぱり必要だとは思いますね。

―山崎さんはどうお考えでしょうか?
山崎:さっき「FRIENDSHIP.がコミュニティーになりつつある」という話をしましたけど、最近はコミュニティー同士をつなげることもやり始めていて。例えば、フランスのアーティストと日本のアーティストをつなげて一緒に曲をつくったり、海外のアーティストとスプリットみたいなかたちで作品を発表して、お互いの国のリスナーに聴いてもらったり。そうやってコミュニティーとコミュニティーをつなげることが、海外とつながる近道になると思います。
FRIENDSHIP.から配信しているフランスのブラスファンクバンドFunkindustryの“Rock This Night”を聴く(Spotifyを開く)
山崎:あと先日IMMF(International Music Managers Forum)っていう、世界5大陸50か国のマネージャー団体のトップと情報交換をする機会があって。そのときに、「ワールドツアーができるアーティストは、アルバムがヒットしているアーティストだ」という話になったんです。
アメリカの年間チャートは、シングルとアルバムのチャートでアーティストがほぼ被ってなくて、ブッキングエージェントはアルバムがヒットしてるアーティストに声をかけて、ワールドツアーを組むと。シングルヒットはあくまで曲ヒットで、アーティストヒットではないので、ワールドツアーを組んでもチケットが売れないことが多いんですよね。
―なるほど。
山崎:そこに海外で活動するヒントがあると思っていて。ぼくらは一曲がどれだけ再生されるかに気を使い過ぎちゃうところがあるけど、最終的には曲ヒットからそのアーティストのファンになって、そこからライブやフィジカルへという流れがあると思うんです。要はもっとアーティストのブランドを高めるプロモーションをしていくことが、結果的に海外でのヒットにつながっていくんじゃないかと思いますね。
世界に向かうには「点」ではなく「面」で。音楽業界全体の課題とは
野田:ぼくらは2016年から『サウス・バイ・サウス・ウエスト(SXSW)』(アメリカで行われる世界最大級のテクノロジーとカルチャーの祭典)でイベントをやってるんですけど、2020年はちょっと形を変えて、FRIENDSHIP.さんと音楽メディアのSpincoasterさんを交えて、向こうで日本人アーティストが出られるイベントを企画してたんです。そうしたら……ギリギリでコロナになっちゃって。
山崎:出発まで一週間切ってましたよね。
野田:ぼく、完全に行くつもりでしたからね(笑)。

―やはり海外にアプローチするためには、連帯も必要になってきますよね。
野田:世界に向かうときは、点で行っても一発で終わりなんで、やっぱり面で、全体で向かわないとダメだと思います。しかも、世界中の国が同じようなことをしようとしているわけで、そのためにもまずは楽曲の数を増やさないといけない。僕がTCJを始めて、最初に「これは日本勝てないな」と思ったのは、「数」なんですよ。
昔よくプレゼンで使ってたんですけど、そもそも海外に流通してる日本の楽曲の数って、世界全体のなかだと乳首くらいだったんです(笑)。このなかからヒットを生み出すのは相当に難易度が高いので、クオリティーは担保しつつ、数も絶対に必要だと思いました。今では世界配信は手軽になり、世界を身近に感じてもらえると思いますが、そのうえで配信だけではなく、ライブやイベントをやったり、全体で世界を考える必要があるなって。
―デジタルディストリビューターも、それぞれのポジションを認識しつつ、業界全体を押し上げる動きができるといいですよね。
野田:海外への対応に関しては、国内のディストリビューターのなかでも結構差があって、パッと見は一緒でも、「このディストリビューターは海外のこのストアには出してない」とかがあるので、そういうことも啓蒙していきたいですね。
ぼくらがつくるアーティストページはマルチランゲージに対応してますけど、今後はアーティストページ一つにしても、ちゃんと海外を意識してつくる必要があります。向こうの検索に引っかからなかったら、情報が存在してないのと一緒ですから。そうやって成功の確率を少しでも上げておくことが、ぼくらの仕事でもあると思います。
山崎:英語で情報を出すことは最低限必要ですし、現地のアーティストと関わることも重要で、やはり活動を限定しちゃうと広がらないから、どんどん外に出て行くことですよね。もちろん、いま実際に向こうでライブをやるのはハードルが高いですけど、SNSを通じて海外のリスナーとつながったりして、コアなファン層にリーチしていくことがまずは重要だと思います。

- プロフィール
-
- 野田威一郎 (のだ いいちろう)
-
東京出身。香港で中学・高校時代を過ごし、慶應義塾大学卒業後、株式会社アドウェイズ入社。2008年に独立しWano株式会社を設立。2012年にはTuneCore Japanを立ち上げ、2012年10月にサービスを開始。
- 山崎和人 (やまざき かずと)
-
1978年生まれ。2000年、株式会社ハーフトーンミュージック入社、2003年よりライブハウス"新宿MARZ"店長/ブッキングマネージャーを経て、2009年に株式会社ヒップランドミュージック・コーポレーション入社。The fin.、LITEのA&R/マネージャーとして、作品リリースやアメリカ、ヨーロッパ、アジアなど数々の海外ツアーの制作を担当。2019年5月より、デジタル・ディストリビューションとPRが一体となったレーベルサービス「FRIENDSHIP.」をスタートさせる。



