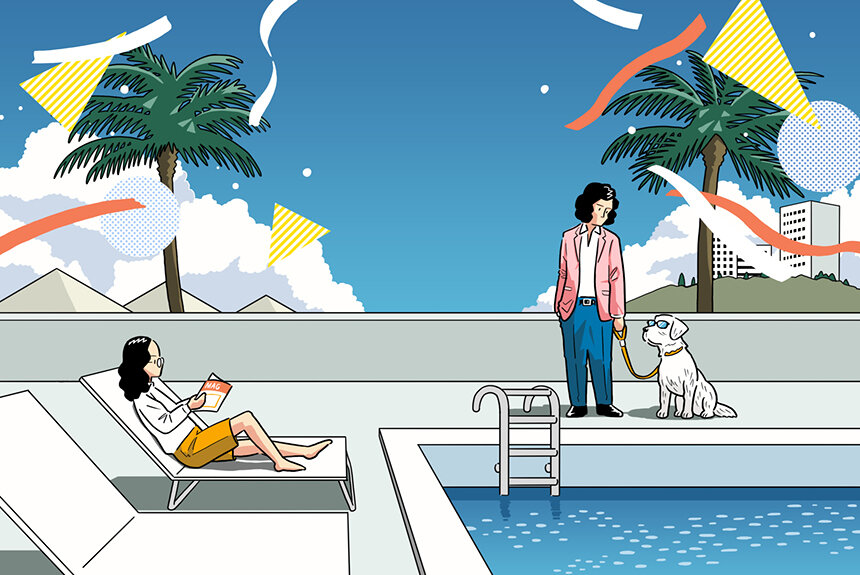「シティポップ」にまつわる言説はとても複雑だ。そもそも音楽的な定義が曖昧で、その反面なんとなくの風景やビジュアル、イメージを想起させてしまう言葉の魔力も理由としてあるだろう。だがもちろんそれだけではない。
たとえば、1970~1980年代のリアルタイム世代の感覚、1990~2000年代にクラブシーンで「和モノ」としてリバイバルされたときの感覚、2010年代初頭に「ネオシティポップ」としてリアルタイムではない世代による実践が盛んに行われていたときの感覚が、そのときどきの社会的状況やメディア環境を反映して微妙に異なっていることもひとつの背景にある(もちろん共通している部分も大いにあるのだが)。
そこに海外からの目線が加わると一層ややこしくなる。ちょうど「ネオシティポップ」という言葉が用いられはじめたころ、インターネット上ではヴェイパーウェイヴと呼ばれる新たなジャンルが勃興し、日本のシティポップが発見され、アメリカの若者たちのあいだでにわかに注目を集める。2010年代にYouTubeなどを通じてアメリカでディグされていったシティポップの感覚と、日本国内における感覚には見過ごせないギャップがあり、そこにもシティポップという言葉にまつわる複雑さを生み出す因子が隠れているように思われる。
ヴェイパーウェイヴを出自に持つ韓国のDJ・Night Tempoや、インドネシアのYouTuberであるRainychといったシティポップを積極的に取り上げるアーティストの存在も忘れてはならない。日本とアメリカという単純な構図で語ることができず、各国の状況も考える必要があるとなると事態はさらに複雑になる。
何が言いたいかというと、「2021年におけるシティポップブームの要因はこれだ」と言い切れる何かを提示することは不可能に限りなく近いのだ。
この認識を前提に、それでもこの興味深い現象の背景を整理して記事にできないかと考えた。『シティ・ポップ 1973-2019』(2019年、ミュージックマガジン)の監修も手がけた松永良平、9月に編著書『シティポップとは何か』(河出書房)の刊行を控える柴崎祐二、そしてSpotify Japanの芦澤紀子に協力いただき実施した鼎談をまとめたのが本稿だ(後日もう1本の記事を公開予定)。
ここでは2010~2020年代のシティポップの海外受容における文脈と背景、そして日本におけるシティポップにまつわる歴史にフォーカスをあててまとめている。それにあたって先述の『シティ・ポップ 1973-2019』と『ユリイカ2019年12月号 特集=Vaporwave』(2019年、青土社)は大変参考にさせていただいた。
この記事があなたにとって、シティポップというミステリアスで魅惑的な音楽の奥にあるものについて考える(あるいは見つめなおす)きっかけになれば幸いだ。
2010年代後半のグローバルなシティポップブームの経緯を概観する
芦澤:まず、Spotify上でシティポップを取り巻く世界的な状況に顕著な変化が見られるようになったのは、2020年の10~11月以降、年末にかけてでした。
いろんな記事ですでに書かれていることと重複するのですが、もともとヴェイパーウェイヴ / フューチャーファンク(註1)的なものの延長線上で、日本のレアなレコードやCDをディグすること、それをネット上で聴くことが2010年代の後半くらいから盛んに行われるようになり、そこにYouTubeのレコメンドのアルゴリズムも影響して、世界中にシティポップのムーブメントが拡散していくんですけど。
柴崎:それと関連して、2010年代を通じて世界の音楽市場において、Daft Punkの“Get Lucky”(2013年発表の『Random Access Memorie』収録)を象徴とするディスコ / ブギーの復権や、AORの再評価など、1980年代的なもののリバイバルが世界的にあったんですよね。
Daft Punk“Get Lucky”を聴く(Spotifyを開く)
柴崎:聴取感覚的にシティポップと近い80sサウンドのリバイバルがあったこと、あるいはヴェイパーウェイヴやフューチャーファンクを経由した1980年代的な音楽に対する欲求が、若年層のリスナーの間にふつふつと溜まっていたこと。そこに極東からのシティポップがネット上で顕在化してきた、という。
芦澤:そうですね。そういった状況のなかで2016年の秋にSpotify Japanはローンチしました。
当初は国内のカタログ音源が全て揃っているわけではなかったのですが、いろんな状況が相乗して2019年くらいからシティポップの名盤とされる作品の配信も増えてきて。
ネット上にある非公式の音源やカバー動画、もしくは非公式に楽曲を使った動画が再生回数を積み上げていくなかで、公式のストリーミング音源も発見されて聴かれるようになっていきました。それが2019年以降から、2020年にかけて。
芦澤:そのあたりから東南アジアを軸とするTikTokのムーブメント、特にRainychの存在も大きいと思うんですけど、どんどんオーバーグラウンドな動きに転化していって、2020年12月に松原みきさんの“真夜中のドア~Stay With Me”(1980年)がいきなりグローバルバイラル18日連続1位という状況につながる。
さらに、竹内まりやさんの“プラスティック・ラブ”(1984年)が世界中でSpotifyで聴けるようになるのが偶然同じくらいの時期で。おおまかにはこういった経緯で現在に至ります。
“プラスティック・ラブ”と“真夜中のドア”の、月と太陽のような関係
松永:以前も書いたんですけど、“プラスティック・ラブ”ってずーっとYouTube上に存在するだけで、「オフィシャル音源」がネット上にないヒット曲だったんですよね。
韓国と日本を行き来しながらDJ / プロデューサーとして活動している長谷川陽平さんに昨年取材した際にも“プラスティック・ラブ”は現場ですごく愛されていて、“真夜中のドア”も同じくらいクラブでの人気があった。太陽と月みたいな関係だったと聞きました。
“プラスティック・ラブ”の解禁は準備されていたこととはいえ、タイミングがすごく不思議というか、偶然の賜物だとしてもすごいことだなと思いますね。
竹内まりや“プラスティック・ラブ”を聴く(Spotifyを開く)松原みき“真夜中のドア”を聴く(Spotifyを開く)
芦澤:“プラスティック・ラブ”はニーズがあることは明らかだったのに、正規の音源が出てこない状況が長らく続いていたところで、2020年12月に解禁されることが決まって。そのタイミングが、“真夜中のドア”のグローバルバイラル1位と一致したのは、偶然なのか必然なのか、と考えますね。
長らく国内の消費だけで成立していた日本の音楽市場に、シティポップがもたらした変化
柴崎:日本の音楽が海外にフラットな視点で受け入れられること――主に業界内でこれまで疑問視されていたことを覆したのは、まりやさん含めてシティポップ系音源だったんだろうなと思うんですよね。
2010年代後半にかけて、レコード会社も「海外に出せるものは出していったほうがいいんじゃないか?」というふうに意識がかなり変わった印象があって、“プラスティック・ラブ”の「公式化」への流れは業界の変化の象徴って感じもします。
芦澤:たしかに。当初はストリーミング配信するにしても日本だけで出すことも多かったですし、それがいまやなるべく世界のユーザーに聴いてもらおうという考えが主流になっている。おっしゃるように、レーベルやアーティストの考え方が変わっていったきっかけともいえると思います。
プレイリスト『City Pop ‘80s』を聴く(Spotifyを開く)
柴崎:日本の音楽産業は国内で自活できるマーケット状況が長いこと続いていたから、現場の人たちも、法務部とか管理系の人たちも日本のポップスの海外へのライセンスアウトとか流通とか、最初は頭になかったと思うんです。これは2000年代にぼく自身がメジャーレーベルのスタッフだった頃の実感でもあるんですけど……(苦笑)。
「まさか、いまみたいなブームになるとは思ってなかった」ってのはレコード会社の人からもよく聞く話なんです。そういった背景を持ちながら、いまシティポップが世界規模で聴かれる状況になったのは、第一にはそれほど魅力的な音楽だからということでもあるわけですよね。
芦澤:そのとおりだと思います。日本以外のマーケットに流通することを見込んで制作されていない鎖国のような状態があったと思いますし、仮にすごくレアなアナログ盤がロンドンのレコードショップに行き着いても幅広く流通することはないですしね。
そういう意味でシティポップ系の音源は「知る人ぞ知る宝が埋もれていた」という状況だったんだと想像します。海外のリスナーは新しく「発見」したというような感覚を持っていますし、若いリスナーに受け入れられていることも、ノスタルジーではなくいまの時代の音楽として新鮮に響いているという証拠なのかなと。
2010年代初頭、国内外で起こったシティポップ再評価。日本では70年代的なものが、海外では80年代的なものが注目されていた
松永:シティポップに対する海外での評価軸はぼくらにとっても発見だったんですよね。2010年前後くらいにシティポップってワードがあらためて持ち出されるようになったときは(註2)、いまとはちょっと違う感覚だったんですよ。もう少し1970年代的なものに寄ってたというか。
プレイリスト『City Pop ‘70s』を聴く(Spotifyを開く)cero“わたしのすがた”(2012年)には<シティポップが鳴らすこの空虚、 / フィクションの在り方を変えてもいいだろ?>という歌詞がある(Spotifyを開く)
松永:そのときは「はっぴいえんど、ティン・パン・アレー、シュガー・ベイブ(註3)的なものに端を発して~」みたいにシティポップについて説明していて、いまでもそれは、はじまりとしては有効だとは思ってるんですけど、ワールドワイドでみんなが享受してる感覚はもっと1980年代的なものですよね。
はっぴいえんど『風街ろまん』(1971年)を聴く(Spotifyを開く)ティン・パン・アレー『キャラメル・ママ』(1975年)を聴く(Spotifyを開く)
松永:ぼくらからすると、竹内まりやさんのアルバム『VARIETY』から“プラスティック・ラブ”一曲だけ切り離して聴く感覚がすごく刺激的だったんですよ。
なぜなら“プラスティック・ラブ”は『VARIETY』のなかでも、長年のファンからは「アルバム全体からは結構浮いている」と言われていた時期が長かったから(笑)。
柴崎:それまでの作品からするとサウンドも歌詞もかなり異端的なものですよね。
松永:そうそう(笑)。シングルカットされてはいたし、当時12インチも出ていたけど彼女の代表曲とはずっと思われてなかった。それが、近年の海外のリスナーの感覚が持ち込まれたことでゲームチェンジしたというか、楽曲としてネット上でひとり歩きしてしまう状況がもたらされた影響は大きいと思ってます。
柴崎:日本国内で連綿と受け継がれているシティポップ観と海外ユーザーの考える理想的なシティポップは、相当な乖離があると思うんです。もちろん潮流ごとに重なっている部分はあると思いますが。
芦澤:そうですね。
柴崎:1990年代半ば以降、特に2000年前後以降の、「ポスト渋谷系」的な世代の作家のあいだでは、シュガー・ベイブ、ティン・パン・アレー、いわばはっぴいえんど一派みたいな1970年代のアーティスト / 作品が「真正」なものとして崇められていた。
その当時の感覚からすると、1980年代のものは、そのあとにバブル景気の狂騒が控えてるのもあって、高度消費社会的で浮ついた、どちらかというと「フェイク」くらいに受け止めていたはずなんですよね。
松永:たしかにその感覚はあったと思います。
なぜ、海外のシティポップリスナーには80年代的なものが好まれるのか?
柴崎:そういう浮ついた感覚を外側から相対化することができる後追い世代=国内外のミレ二アル世代以降の感覚と、80sサウンドの広範なリバイバルが共振したことによって、フューチャーファンクが支持を拡げ、次いで日本のシティポップ自体が発見された、と考えることもできるかも。
しかも日本の1980年代は安定成長期でテクノロジー大国になりつつあった他方、貿易摩擦を起こして世界でその経済力が脅威としても認識されていて。
各地域で1980年代の高度消費主義は、日本的な表象として、集団的記憶として刻み込まれてるんじゃないかと思うんですよね。社会学者のエズラ・ヴォーゲルが1979年に出した本のタイトルですが、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』って言葉が喧伝されたくらいで。
柴崎:いま“プラスティック・ラブ”を聴くときに、そういう集団的記憶を刺激するであろう言葉=「プラスティック」が入っているのは相当大きかったんじゃないかなと思っていて。
好意的に解釈すれば、世界中が好況に沸いていた高度消費社会の楽観主義みたいなものが、ポジティブなものとして――いまは失われてしまっているからこそ逆説的に輝くポジティブさとして、蘇ってきたというべきか。ぼく自身もミレニアル世代に属しているので、その感覚は確かに理解できる。
松永:「ノスタルジー」というワードは海外の記事や発言を見ていてもかなりの頻度でありますよね。自分たちは体験していないけど豊かだったの時代に逃げ込みたいと思う、ある種のエスケーピズムというか。
あと、リスナーがエッジーな刺激を求めた結果というよりは、「すごく洗練された音楽を日本という国で見つけた、楽しい! 気持ちいい!」っていう聴き方をしてる人が多いと思うんですよね。
でも一方で、そこには技巧や技芸みたいな面での刺激あるんだろうなとは感じますし、それは「ヨットロック」(註4)の受容のされ方にも通じることだと思います。別に80s的サウンドでなくても「うまさ」は海外でウケる重要なファクターでもあるわけだし。
佐藤博『Awakening』(1982年)を聴く(Spotifyを開く)プレイリスト『Yacht Rock』を聴く(Spotifyを開く)
柴崎:それはとてもわかります。ベッドルームミュージック的な心地よさだけじゃない、ミュージシャンの演奏技術やクラフトマンシップを見知らぬ曲で発見した驚きと新鮮さ、ということですよね。単にチルするためのBGMとして聴いている人もいるかもしれないけど、一方では決してそういう消費のされ方だけでもない。
松永:そうですね。そこは20年ぐらい前にぼくらがソフトロックとかボサノバに対して感じてたこととそんな離れてない気がします。
柴崎:たしかに。ソフトロックはいまや「松屋の朝のBGM」だけど、そもそもめちゃくちゃ緻密な音楽なわけで(笑)。でも、よくよく考えてみるとBGMって、聴取と情景の間にいらぬ摩擦が起きちゃいけないから、最もウェルメイドじゃなきゃいけないわけなんですよね。
だとすると、いま海外でシティポップを聴いてる人たちは、ムード音楽的に聴く一方で、「この人たち、めちゃくちゃ演奏 / 歌が上手い!」みたいな感覚も持っていてもおかしくはない。
松永:「Light In The Attic」(註5)で今年出たジャパニーズコンピレーションの新作『Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism & Shadow Sounds Of Japan 1980–1988』には、またその先を探しはじめてるセンスも感じます。
シティポップとニューウェイブ、アンビエントの間、みたいな。シティポップのなかにもうちょっとエッジの立った感覚というか、ポストパンク的なものを入れていこうとしてる人たちもいる感じなのかなと最近は思ってます。
『Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism & Shadow Sounds Of Japan 1980–1988』(2021年)を聴く(Spotifyを開く)
2020年、松原みき“真夜中のドア”が起こしたTikTokバズの意味するところ
松永:もしかして2020年がコロナの年じゃなかったら、いまの海外でのシティポップのブームも内向的な方向とダンスミュージック的な肉体性とか、グルーヴのほうに分かれたかもしれないなとは思ってるんですけど。
当山ひとみ『SEXY ROBOT』(1983年)を聴く(Spotifyを開く)角松敏生がプロデュースを手がけたJADOES『Free Drink』(1987年)を聴く(Spotifyを開く)
柴崎:「現場」の音楽としてもっと盛り上がっていた可能性が。
松永:そうそう。これもまた時代の歯車の噛み合わせの妙っていうか、不思議な偶然ですよね。
柴崎:たしかに、クラブイベントとかフェスでシティポップによるダンス体験共有の可能性が剥奪されてしまったのは大きいですよね。
仮説でしかないですが、TikTokでのバズとか、Spotifyでのバイラルヒットが顕在化したきっかけとしては、この間コロナでリアルのパーティーできなかったことはあるかもしれない。
芦澤:TikTokのバズがバイラルに波及してストリーミングでヒットになってく流れが顕著になったのは、偶然かもしれないんですけどコロナの時期と世界的に一致していますね。
松永:ぶちアガっていく画が現実になる未来があったんだなぁと思いはしますね。
そもそもいまのシティポップブームの少し前には世界的なディスコブギーのブームもあったわけだし。イギリスの大きなフェスでDJが“真夜中のドア”をかけてぶちアガった動画がYouTubeにアップされてさらにバズるとか。でもステイホームで人が集まれない状況もあって、TikTokのほうが波及しやすいというか、より草の根的に広まっていったんだろうなとはすごく感じます。
松永:シティポップはライブ的な一回性とか共通体験みたいなものから離れたところで、海外で生き延びていく活路を2020年に改めて得てしまったんじゃないかって気もします。
柴崎:一方で、シティポップを現場で盛り上げてきたクラブカルチャーの側に立つと、こういう状況になって、現場でパーティーの場が持てないのはかなり惜しいですよね。
シティポップブームの土壌をつくった日本のクラブシーンにおける「和モノ」の文化
柴崎:ぼくも年齢的に現場に間に合えたわけではないですけど、DJ現場における「和モノ」(DJプレイできる邦楽レコードのことを指す)再評価の流れって、渋谷系初期みたいなときからグループサウンズとか歌謡曲をクラブでかけたりとか、いろいろあったわけじゃないですか。
松永さんが『レコードコレクターズ』で書かれていましたけど、1990年代にロンドンのシーンには山下達郎を回すDJがいた、みたいなこともあった。
松永:実際、1990年代にDJ用のブートレッグに“Dancer”(1977年に山下達郎が発表した『SPACY』の楽曲)が収録されているのを見たこともあります。たしか、アーティスト名は「SPACY」になってた(笑)。
柴崎:1990年代の時点で、シティポップの海外需要の土壌となるものが既にあったということになりますよね。
そのあと国内でも、木村ユタカさんのディスクガイドが2000年代前半に出たり(2002年刊行の『ジャパニーズ・シティ・ポップ』)、ダンスミュージック的なビートを強調したシティポップの実践として流線形が出てきたり、MR.MELODYやXTALさんがダンスミュージックの解釈としてシティポップのミックスをつくって、日本のフュージョンとかシティポップをGファンクとかハウス的な感覚で聴くことを提示したり、みたいな。
他にも、okadadaさんが長年やっているイベント『ナイトメロウ』とか、いろいろと例はありますけど、すごく芳醇な前史が蓄積されているんですよね。
流線形『シティミュージック』(2003年)を聴く(Spotifyを開く)
柴崎:現在の国外の感覚に直接的に流れ込んでいるわけではないだろうけど、少なくとも日本国内におけるディグやプレイの蓄積があったうえで、いまのような状況がある。
そういう下地をつくったパイオニアの功績は非常に強調しておきたいですよね。ネットのおかげで、いきなり0から100になったっていうことではない。
松永:そう思います。クラブでの人気を背景に再発が出たり、シーンとして盛り上がるという構図は海外でも日本でも同じですしね。
柴崎:そうですね。
柴崎:さっきも触れましたが、1970年代的なロウな「プレ・シティポップ」=シティミュージックに対する評価は1990年代半ば以降脈々とあって。
松永:むしろその頃はそれしかなかったような。
柴崎:シュガー・ベイブの『SONGS』(1975年)は聖杯化が進んでいるけど、『FOR YOU』(1982年に発表された山下達郎の6作目のアルバム。代表曲のひとつである“SPARKLE”などを収録)のレコードは激安で買える、みたいな感じですよね、その頃は(苦笑)。
松永:そうそう。達郎さんも含めて、日本の1980年代の音楽は長い間見過ごされてたと思いますよ。それがまさか、日本のロックのレア盤セールのトップを飾るようになるとは。
柴崎:その価値転換がすごくドラスティックに行われたのがフューチャーファンク以降だったとすると、やっぱりさっき挙げたDJのみなさんはその先駆として重要だと思うんですよね。
その鼻の利き方は本当にすごいと思うし、折々で一番見過ごされてるものから良質なグルーヴを発見してくる「レア・グルーヴ」の最も優れた実践のひとつだなとも思います。
松永:MR.MELODYさんやXTALくんがシティポップでミックスをつくったのも、安いものからものすごくかっこいいものをつくり出すって行為を粋に感じたからだとも思う。
ヒップホップがそうであったように、安く売られている、入手しやすいジャンク的なものから新しいものを発見する人たちがアンダーグラウンドなところから新しい文化を生み出してきた歴史があるけど、シティポップではそれと同じことがBOOKOFFで起きたんだとぼくは理解していますね。そこに海外からのデジタルな発見がかぶさってきたという流れ。
「過去の音楽を発掘する文化の運動自体がはらんでるダイナミズムも同時に語っていかないといけない」(柴崎)
柴崎:サブスクリプションって、ある意味ではとてもデモクラティックなツールだと思うんですけど、一方で「安いもののなかから珍しくてすごいものを探す」みたいなフィジカルメディアの分布勾配を前提とするレア・グルーヴ的な運動は起こりづらくなるんだろうなと思うんですよね。
最後のフィジカル世代の人間としては寂しさも若干あったりして(笑)。もちろん、馴染みのない地域の音楽やマイナーなジャンルを手軽に探求できる快感はストリーミングならではだと思うんですけど。
プレイリスト『City Pop ‘90s』を聴く(Spotifyを開く)
芦澤:コレクターのニッチな宝探しの喜びみたいな側面の強かったディグという行為に対して、われわれストリーミングサービスは誰もが等しく聴くことのできるものとして楽曲を提供しているわけで。
SNSなどで楽曲がシェアされたり、使われたりということを通じて爆発的な浸透がある一方で、損なわれてしまう部分もあると感じる方もいるのかもしれないですね。
柴崎:どうしてこんなことを言うのかというと、「シティポップ、世界中でバイラルヒットしてめでたいね」だけだと、結局マーケティング論みたいなところばかりに回収されていってしまうと思うからなんです。音楽内容そのものの面白さを探求していく方向がないと、あとに続く面白い動きもなくなっちゃうんじゃないかという気もするんです。
過去の音楽や、ニッチなものを発掘するっていう文化の運動自体がはらんでるダイナミズムも同時に語っていって、ストリーミング時代ならではの「宝探し」の面白さを探求したい気持ちがあります。
松永:そうですね。シティポップって「こうじゃなくちゃいけない」というジャンルではないので拡大解釈がどこまでも可能。
だからこそ、「宝探し」の快感のありかを継承したり独自に伸ばしたりできる可能性がある。「これもシティポップだ」って言うのは自由。だからいまは重要なタイミングだなとは思いますね。
シティポップという言葉に含まれるナショナリズム的な危険
柴崎:あと、これは自分を含めて日本のジャーナリズムに対して釘を刺しておく意味で、現在のシティポップバブルって、過度な「日本ボメ」みたいな欲望、もっと直接的に言えばいびつなナショナリズムみたいなものと結びつく危険性もあると思うんです。
たとえば、アジア各地のメロウな音楽を、背景の文脈を無視してなんでもかんでも「〇〇(国名)シティポップ」みたいに言うこともあるけど、そこに、ぬぐいがたい日本中心主義みたいなものを感じてしまったりもして。
あとは、「アジア各国で日本のシティポップが流行っているのは、彼らが、かつてシティポップが流行していた時代の(憧れの的であった)日本の経済力にようやっと追いついてきたからだ」みたいな見方もあったり。いや、ことはそんな単純じゃないだろう、という。
もちろん「シティポップ」という言葉自体がバイラルに広がっていることは健全な状況だと思うんだけど、少なくともジャーナリズムや産業側の人間はその行き過ぎに関しては神経質になるべきなんじゃないかなと思うわけです。
松永:そうですね。そこは文脈の跳躍が起こってることにも関係していると思っていて。「いま世界で流行しているシティポップは、日本で1970~80年代につくられた音楽です」としたときに、安直に「昔の日本はすごかった」に文脈が跳躍しているというか。
もともと日本でシティポップと呼ばれていた音楽は、アメリカやイギリスのAORや、ソウルミュージックから影響を強く受けたもの。海外で起きている流行を率直に取り入れてゆくという命題があったわけで。
柴崎:ブラックコンテンポラリーとかAORみたいなメロウな音楽が世界的に覇権を持っていた1980年代は、世界同時的に日本もアジア各国もアジア以外も、やっぱり欧米、とくにアメリカのヒット曲から影響を受けていたわけで。よくも悪くもですが。「シティポップ」って言葉だけをひとり歩きさせると、そういう1980年代の前提的な文脈が剥奪されておかしなことになってしまいますよね。
Filtr Japanによるプレイリスト『Best of AOR CITY』を聴く(Spotifyを開く)国分友里恵『Relief 72 hours』(1983年)を聴く(Spotifyを開く)
柴崎:だから、シティポップブームを寿ぐのはいいのだけど、それが「日本スゴイ論」に回収されるのは個人的にすごく違和感がある。トランスナショナルなものとして人をつなぎつつあるシティポップのポジティブな機能を毀損することにもなるんじゃないかと。
これは主にわれわれジャーナリズム側の責任なんですけど、うまく対応していかないと、そのうちガハハおじさんみたいな人たちが「よくわからんがシティポップの企画出しとけ!」とか言い出しかねない(笑)。
松永:まあ、すでに各レコード会社でそんな狂騒がはじまってるっぽいですけどね(笑)。
柴崎:「日本は、西洋の文化を上手く消化して、他アジア地域に再流通させる最も優秀なハブを担ってきた」っていう、いわゆるハイブリティズムっていう概念が伝統的にあって。
これって、あえて乱暴にいれば、「先生(アメリカ)のいうことを普通の生徒たち(他アジア所属)に噛んで含むように教える優秀な学級委員のぼく」みたいな、そういう言説なんですけど……。
「日本ボメ」文脈におけるシティポップって、「西洋の再解釈は日本がいちばんうまくて、他の東南アジア周辺の連中はそれを享受してる」みたいないびつな世界観すら簡単に描けてしまうマジックワードなんですよね。だからそこに関しては相当自制的に考えていかなきゃいけないなという気持ちがあります。
松永:それはすごくわかります。
海外のリスナーは、シティポップをオリエンタルなものとして聴いているのか?
松永:ただ、かつて日本の音楽というと、ある種のオリエンタリズム、エキゾチズム(註6)に彩られたものしか欧米のマーケットではウケにくいとみなされていた状況があったじゃないですか。
尺八や琴の音を使ったフュージョンとか。それはそれでオリジナリティがあるし、ぼくも好きなんですけど、そういう傾向が強かった時代からするといまのシティポップは、古風なオリエンタリズムを押し出さずにヒットしている稀有な例かもと思いますね。
柴崎:YMOも「セルフ・オリエンタリズム」的な意匠を打ち出していたわけで。
松永:そうそう。
柴崎:海外から向けられた日本への視線を内在化する、っていう転倒的なもの。それを批評的にやっていく方向性が当時の海外向け戦略のデファクトスタンダードでもあった。
Yellow Magic Orchestra“東風”(1978年)を聴く(Spotifyを開く)
柴崎:でも多くのシティポップ系アーティストたちは、そういうセルフ・オリエンタリズム的な戦略をやろうとはしてなかったわけで。むしろコスモポリタンな意識で、自分が好きな米国産音楽から素直に影響を受けた音楽をやっている、という意識だったはずで。サウンドはストレートに海外志向だけど、それゆえに意識的に海外マーケットを射程に捉えた音楽ではなかった……という逆説がある。
いまそういうものがブームになっている状況は、松永さんがおっしゃったような「ハラキリ」「ゲイシャ」みたいな古典的なオリエンタリズムが衰微して以降、要するにポピュラー文化の流通において西洋が絶対的な覇権を失ったインターネット以降の興味の持たれ方だと思うんですよね。
松永:たしかにね。
柴崎:一方でさっき話した「1980年代のポジティブさ」の裏面として、初期のヴェイパーウェイヴで顕著に見られる表象なんですが、1980年代以降の「テクノ・オリエンタリズム」(註7)のようなもの――要するに、テクノロジー大国たる日本の表象が無機質で不気味なものとして捉えられるという、いわば更新されたオリエンタリズムが、シティポップブームのなかも受け継がれているようにも思っていて。
Yellow Magic Orchestra“テクノポリス”(1979年)を聴く(Spotifyを開く)
柴崎:映画『ブレードランナー』(1982年公開、原作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の初版は1968年)とかウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』(初版発行は1984年)みたいなサイバーパンク的世界観における日本的要素の描写を思い浮かべてもらえればわかりやすいんですが、もしかしたら、そのテクノ・オリエンタリズム的な感覚自体が、集合的なノスタルジーとして西欧社会でリバイバルしてる可能性もあるのかなと思うんです。
松永:あの当時の作り手が持っていた「ものすごく強い西洋への憧れ」が玉手箱のなかで保存されたままになっていて、その輝きだけが現代にビカビカっと届いてる。時間も場所も離れたところにいるリスナーにはその強さが不思議だし魅力的に見えるんでしょうね。
さまざまな文脈が絡み合う海外でのシティポップ評価を、われわれはどのように捉えるべきか
柴崎:なぜそれがリバイバルしたかというと、いま欧米すらも黄昏ているなかで、1980年代当時の日本の、高度資本主義が高速で回転している広告型社会のあり方が、ノスタルジアの対象になってるんじゃないかと思うんです。そこには、ある種の自虐のような気持ちもありながら(註8)。
あえて意地悪く言うと、日本の経済的な失墜があったからこそ安心して心をくすぐられるというか、結局テクノ・オリエンタリズム的な世界観は完徹されなかったっていう西洋社会のいびつな安堵感もあるのかもしれない。そういう意味では、オリエンタリズムも未だかたちを変えて残存してるのかもしれない。
松永:そこは全然否定できない気がします。もちろんいまは強いリスペクトにかたちを変えてはいるんだけど。
柴崎:それは欧米の音楽ジャーナリズムでもある程度自覚されている論点のようで、『Pitchfork』とか『VICE』とかのシティポップの記事を見てると、そこに切り込もうとする論調のものもあったり。
一方で、現場でレコードをプレイしているの人のなかには、「いやいや、われわれは子どもの頃から日本のアニメとかいっぱい見てるから、そんなオリエンタリズムみたいな気持ちは別にないし」みたいに反駁する例もある。そして、それも説得力がある。
松永:たしかに、「Adult Swim」(アメリカのアニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」の夜の放送枠)って割と重要で。
Thundercat世代のアメリカのミュージシャンに話を聞くと、あの時間帯に日本のディープなアニメを見て感化され、そこから他のカルチャーも深掘りしたって言う人は多いんですよね。『カウボーイビバップ』(註9)とかが向こうで人気出たのはその枠だったからだし。
プレイリスト『カウボーイビバップ』を聴く(Spotifyを開く) / 関連記事:『カウボーイビバップ』のサントラと、優れた音楽演出(記事を開く)
柴崎:もちろんはっきり分けることのできないグラデーション的な状況だとは思うんですけど、かつての日本産シティポップがそういうふうにまなざされている可能性もある、ということは言っておきたいですね。
「ポップスの本場たる西洋に認められた、やったー」ってことじゃなくて、非常に複雑な意識がかたちを変えて存在している可能性もある。そこへの想像力を持っといてもいいんじゃないかって、これはわれわれジャーナリズム側の話なんですけど(笑)。
松永:うんうん。そうですね。
柴崎:すみません、ちょっとややこしい話になりました。
松永:でもこれはすごく大きな問題ですよね。
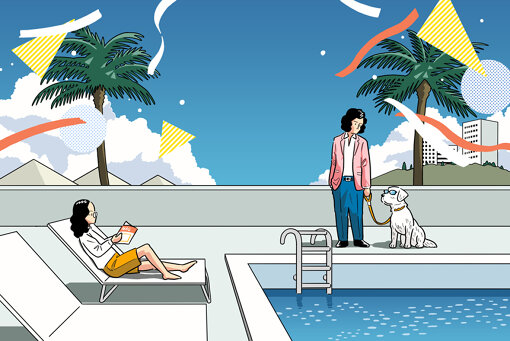
編註と参考文献
▼註
1:ヴェイパーウェイヴとは、「1980年代のポップスや店内BGMなどの音源の音質やスピードを落とし、延々とループさせる音楽のジャンルとされている。シティポップの文脈で話題になり、ダンスミュージックとして扱われているFuture Funkもその派生ジャンルと言われている。支離滅裂な日本語や、1990年代のローポリゴンCGを多用したデタラメながら強烈なアートワークも特徴」――著・佐藤秀彦 / 編・New Masterpiece『新蒸気波要点ガイド (ヴェイパーウェイヴ・アーカイブス2009-2019) 』より(サイトで見る)
2:『CDジャーナル』2012年11月号上で松永は、cero“わたしのすがた”にある<シティポップが鳴らすこの空虚、 / フィクションの在り方を変えてもいいだろ?>という一節をきっかけに磯部涼と「あたらしいシティ・ポップ」と題した対談を実施している
3:はっぴいえんどは、大滝詠一、細野晴臣、鈴木茂、松本隆からなる日本のロック黎明期のバンドで、1971年に発表した『風街ろまん』は日本のロックの金字塔として名高い
ティン・パン・アレーは荒井由実などの演奏やプロデュースも務めたプロデューサーチーム。はっぴいえんどの解散後に細野晴臣のソロアルバム『HOSONO HOUSE』(1973年)のレコーディングに集った鈴木茂、林立夫、松任谷正隆によってキャラメル・ママを結成、のちに改名してティン・パン・アレーとなった(参照:『ロック画報 14』P.12)
シュガー・ベイブは、『キャラメル・ママ』(1975年)や荒井由実『MISSLIM』(1974年)などでコーラスとコーラスアレンジで才能を発揮していた山下達郎、そして大貫妙子を中心としたバンド。『SONGS』(1975年)という1枚のアルバムを大瀧詠一主宰の「ナイアガラ・レーベル」よりリリースして解散。シングルとして発表された”DOWN TOWN”は1970年代のシティポップを代表する1曲として知られる(参照:萩原健太『70年代シティ・ポップ・クロニクル』)
4:ヨットロックとは、「日本でいうAOR的な音楽のこと。2005年に配信されたインターネットのコメディ・シリーズが口コミで広まり、『ヨットに乗るヤッピーが聴きそうな音楽』という、揶揄的なフレーズだったこの言葉が、アメリカの若い音楽リスナーやDJたちが、あらためてこのジャンルにスポットを当てるきっかけとなった」――『ヨット・ロック AOR、西海岸サウンド黄金時代を支えたミュージシャンたち』書籍説明より(サイトで見る)
5:「Light In The Attic」は、質の高いリイシューをリリースすることに重点を置いたアメリカ・シアトルに本拠を置くレーベル。「Japan Archival Series」と銘打ち、1969年~1973年に発表された日本のフォークとロックにフォーカスを当てた『Even A Tree Can Shed Tears: Japanese Folk & Rock 1969-1973』(2017年)、シティポップをテーマにした『Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1976-1986』(2019年)、アンビエント / ニューエイジを取り上げた『環境音楽 = Kankyō Ongaku (Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980 - 1990)』(2019年)というコンピレーション作品をリリースしている
6:松永はCINRA.NET掲載の「2020年のYMO評 エキゾ、電子音楽、ポップスの視点から3人が紡ぐ」で、エキゾについて「アメリカで生まれた『エキゾ』という感覚は、『遠い世界の出来事を想像する感覚』から、この日本で『生活を異界化させる感覚』に変化したとぼくは感じている」と書いていた(記事を開く)
7:テクノ・オリエンタリズムとは、「日本」という表象がいかにして、ネットワーク、サイバネティクス、ロボット、人工知能、シミュレーションといった未来のテクノロジーと同義語になってしまったかを表現するために、イギリスの学者デビッド・モーリーとケビン・ロビンズによって用いられた造語(参照:『Pitchfork』The Endless Life Cycle of Japanese City Pop)
8:初期ヴェイパーウェイヴを代表するアーティストNew Dreams Ltd.こと、Vektroidはこのように語っている。「この二〇年間で世界はゆっくりリアリティがなくなってきているようで、そのことが私を魅了するのです。この二〇年間で起こってきたあらゆることには、潜在的にシュルレアリスムの要素がかなりあります、特に日本で起きたことには。当時の人々に響いたように、今の人々に響くシュルレアリスムの要素を捕らえたいと思っています。例えば、その当時、人々が広告に費やしていた時間の長さは、私には衝撃的です」――『ユリイカ 2019年12月号 特集=Vaporwave』収録のアダム・ハーパー執筆 / Chocolat Heartnight訳「Vaporaveとヴァーチャルプラザのポップアート」(原文はレビューサイト『DUMMY』にて2012年7月に公開)より
9:『カウボーイビバップ』のEDテーマである“THE REAL FOLK BLUES”を歌う山根麻衣が1980年に発表した1stアルバム『たそがれ』は、シティポップの名作として語られることも多い
▼参考文献
『シティ・ポップ 1973-2019』(2019年、ミュージックマガジン)(サイトで見る)
『ユリイカ2019年12月号 特集=Vaporwave』(2019年、青土社)(サイトで見る)
『Light Mellow和モノSpecial ~more 160 items~』(2018年、ラトルズ)(サイトで見る)
『Pitchfork』The Endless Life Cycle of Japanese City Pop(外部サイトを開く)
『VICE』The Guide to Getting Into City Pop, Tokyo’s Lush 80s Nightlife Soundtrack(外部サイトを開く)
- プロフィール
-
- 松永良平 (まつなが りょうへい)
-
1968年、熊本県生まれ。大学時代よりレコード店に勤務し、大学卒業後、友人たちと立ち上げた音楽雑誌『リズム&ペンシル』がきっかけで執筆活動を開始。現在もレコード店勤務のかたわら、雑誌 / ウェブを中心に記事執筆、インタビュー、ライナーノーツ執筆などを行う。
- 柴崎祐二 (しばさき ゆうじ)
-
1983年埼玉県生まれ。音楽ディレクター、評論家。編共著に『オブスキュア・シティポップ・ディスクガイド』、連載に「MUSIC GOES ON 最新音楽生活考」(『レコード・コレクターズ』)などがある。2021年9月に編著を務めた『シティポップとは何か』(河出書房)の刊行を控えている。
- 芦澤紀子 (あしざわ のりこ)
-
ソニーミュージックで洋楽・邦楽の制作やマーケティング、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)で「PlayStation Music」の立ち上げに関わった後、2018年にSpotify Japan入社。